 |
11月23日(月/祭日)四万十市社会福祉センターにて、「環境について」の講演、環境に優しいエコ水(におい消し液)の作り方を教わりました。講師は四万十町より井上先生をお招きしました。 赤潮は家庭から流れる生活排水が原因で海が汚れてだんだん環境破壊をしてしまいます。世界中のみんなが、一人一人力をあわせて海をきれいにしましょう。一人でも多くの人が、エコについて考えていきましょう。というお話をされました。 |
 |
『ゆずり葉』映画は、平成22年3月13日(土)午後6時30分から宿毛市文教センターにて上映された。 |
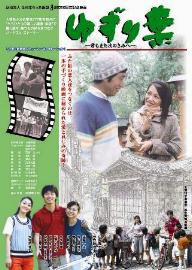 |
 |
北海道の札幌市の一区は凄いよ。先輩方が頑張って来たろう運動を健聴者に見てもらいたい。手話サークルが健聴者にろう者を理解するために呼びかけた。400人位の健聴者が見に来てくれたと…これは凄いなと思った。 |
| 日時 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|
| ・ 4月11日(日) | 定期総会 &消防講習会 主催:手話っち! | 宿毛市社会福祉センター |
| ・ 7月19日(月) | バーベキュー | 愛南町 |
| ・10月11日(月) | そば作り体験 | 松葉川 |
| ・12月11日(土) | 忘年会 | 黒潮町 |
| 2011年 | ||
| ・ 1月 2日(日) | 新年会 幡多聾学校同窓会 | 四万十市 |
| ・ 2月 未定 | 法律相談講演会 |
 |
11月29日と30日(土・日)2日間、 宿毛市社会福祉センターで『竹尾手話勉強会』を行いました。 |
 僕たちがデカイのを釣ったぞ!!
僕たちがデカイのを釣ったぞ!!|
・お天気は曇り晴れ。 ・風は強。 ・波はやや荒波。 ・若潮、 満潮6時56。 干潮11時23。 |
ハリスが何回も切れた。 ・大月の一切港、真ん中堤防。 ・糸4号、ハリスが3号、グレバリ8号。 Nさんが今マダイ55センチ3匹。 当たり 当たり(午前10時頃) |

|
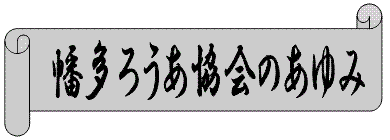 No. 11
No. 11
 |
11月29日(日)宇和島市総合福祉センターで毎年行われている手話のつどいは、今年で手話サークルの「はまゆうの会」が結成して30周年を迎えたので「記念のつどい」を開催しました。平成19年11月に秋の叙勲にて緑綬褒章を受章されました。【おめでとうございます】 講師の高島氏は2回来られた事ありました。地元の人は10年ぶりに会えたのでとても親しみのある交流風景でした。 |
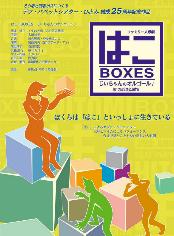 |
 |
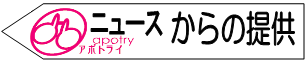
|
● テレビ、新聞の花粉飛散情報に注意する。 ● 使い捨てマスクを使用する。 ● 眼鏡、ゴーグルをつける。 ● 花粉が体に付きにくいスベスベした生地の服を着る。 |
 |
|
ストレスや疲れをためないよう食事や睡眠にも注意しましょう。 症状がひどい場合はのみ薬、目薬、鼻に噴霧(きりふき)する薬など症状を軽くする薬があるので早めに病院へ行きましょう。 |
 |
|
・「懐中電灯!!」 ・「冷蔵庫、冷凍庫が腐るね(~_~;)」 ・「懐中電灯を決まった所に置く」 ・「寝る時は布団近くに置く」 ・「キャンプ用ランタンを使う」 ・「埋込日常照明がついてるから安心」 ・「発電機を利用」 ・「ろうそくはいいけど、火事に気をつけよう」 ・「ご飯は携帯ガスコンロで料理」 ・「メールする」 |
 |
 |
|
・「飲み水だけ買っておく。風呂水は溜めておく」 ・「水道の断水連絡メールに登録したので、今後どうなるか、状況を知らせてくれる」 (水道課にFAXしたら個人のアドレスを職員が手入力でしています。) |
 |
|
蛇口をひねれば、いつだって出てくる水道水。私たちは、それが当たり前の日常を過ごしている。 しかし、あるとき突然、蛇口をひねっても水が出てこないということがあるかも。 ◆日頃からペットボトルの飲料水など購入して備えておきましょう。 ◆トイレの水も、出ませんので日頃からお風呂のお湯が使えるように貯めておくと安心。 |
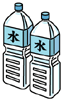 |
 |
 |
 |
 |
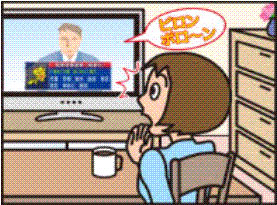 |
 |
家庭では 頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してください。 あわてて外に飛び出さないでください。 無理に火を消そうとしないでください。 |
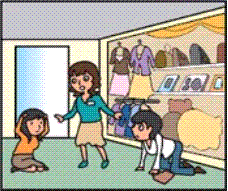 |
人がおおぜいいる施設では 施設の係員の指示に従ってください。 落ち着いて行動し、あわてて出口には走り出さないでください。 |
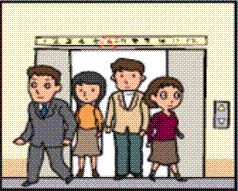 |
エレベーターでは 最寄りの階で停止させて、すぐに降りてください。 |
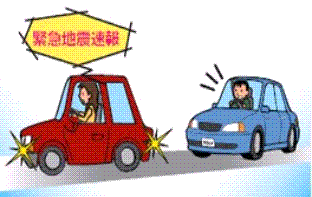 |
自動車運転中は あわててスピードを落とさないでください。 ハザードランプを点灯し、まわりの車に注意を促してください。 急ブレーキはかけず、緩やかに速度をおとしてください。 大きな揺れを感じたら、道路の左側に停止してください。離れる時はキーをつけたままにしてください。 |
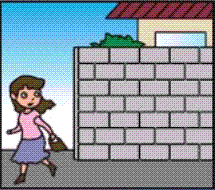 |
街中では ブロック塀の倒壊等に注意してください。 看板や割れたガラスの落下に注意してください。 丈夫なビルのそばであれば、ビルの中に避難してください。 |
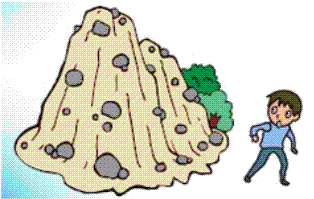 |
山やがけ付近では 落石やがけ崩れに注意してください。 |

私が一貫して、手話で話すことにはちがいないが、一方、ろう者の場合は手話で話したり声を使ったりする。私がはなれた所にいる時に、ろう者は声を出して私を呼ぶ。「なぁ、なぁ」これは、私には使えない。― ろう者だけに許された飛び道具である。聴者には耳がある。耳が使えると思っていても、実は耳は自分の為だけではなく相手が使うためにもある。私は相手の耳には期待出来ないから、当然声で呼ぶことはしない。だから、歩いて行って、手話で話す。向こうは、声を出せば、私の耳を使うことができる。私が使うのじゃなくて、相手が使う。ああ、そういう耳の使い方もあるんだなと思った。今の私の実感は、二人のために共有しているという感覚です。「“聴者だけが便利で、ろう者はいつも不便”ではなく状況によっては、逆になるんだ」と…ちょっとショックです。 K子 |