
『布わらじ作り』のプロ・赤澤先生の指導を受けて、色とりどりの布わらじを作った。
みんな楽しそうに嬉々としてわらじ作りに励んでいる。
やはり手作りは楽しい!と実感!。
終わりに赤澤先生は「台所などで使用すると、床がきれいになる。
汚れた『わらじ』はネットに入れ洗濯するといい」と教えてくれました。
 |
『布わらじ作り』のプロ・赤澤先生の指導を受けて、色とりどりの布わらじを作った。 みんな楽しそうに嬉々としてわらじ作りに励んでいる。 やはり手作りは楽しい!と実感!。 終わりに赤澤先生は「台所などで使用すると、床がきれいになる。 汚れた『わらじ』はネットに入れ洗濯するといい」と教えてくれました。 |
 |
今年6月から、通訳者養成講座『応用課程』を受講しています。昨年受講した『基本課程』から、手話表現技術がますます難しくなったことはもちろんのこと、手話通訳に必要な専門用語も含めた手話語彙が多くなりました。受講したことを復習しようと思うのですが、ノートに書き写すことがやっとで、何度も挫折しそうになりました。講座が日曜日ということもあって、家庭にも負担をかけていますが、家族の「頑張ってきいや!」という言葉に背中を押してもらって続けられています。家族に感謝!感謝!です。 手話通訳者養成講座を受講して、「手話で話ができること」「手話通訳ができること」の違いを実感しています。テープを聞いて…、ビデオを見てテーマを考えたり…、要約を作る作業では、ポイントがつかめず四苦八苦しました。改めて自分の国語力・日本語力の貧弱さを痛感!。今更ながら、もっと本を読んでおけば良かったなぁと後悔しています。 |
| 手話通訳とは、メッセージを受容し、それを理解し保持する。そして保持したものを他言語で再編成し、表現するという過程を繰り返し、しかも同時に重ねて行なう作業です。とても高度な技術なので、私にはまだまだかなりの訓練が必要です。 読み取り・聞き取り通訳では、専門用語や、広い知識が必要とされますが、話し手の生きて来た時代背景や、とりまく環境などを知ることで、表情などから読み取れることは何か?、何を伝えたいのか?を見極める力、伝えようとする気持ちが必要だと思いました。そのためには、多くの聴覚障害者の方々と交流すること。障害者福祉の歴史など知識を深めることが大切だと思います。手話通訳技術以外、もう一つ大事な『講義』も頑張って学びます。 |
土佐清水市の主催する手話教室の仲間たちで、手話サークル『みらい』を発足させ、さらに発展して、奉仕員養成講座を受講し終え、現在、通訳者養成講座『応用課程』を受講しています。 昨年『基本課程』を終了したのですが、応用となると、テキストには細かい単語の説明もなく、手話語彙の少ない私には厳しい講座となります。毎回講座中では、友達や先生方が使う見慣れない手話、テキストに沿って出てくる手話に集中しますが、それだけでは到底追いつきません。家庭学習が必要なのは分かっていますが、今はなかなか出来ていません。 読み取りは、その方の癖やスピードに対応するのが難しい。聞き取りは、記憶力が特に重要だと思います。どちらも手話単語の見落としが多く、私の一番の課題です。手話単語も読み取れないのに、正確に情報などを伝えることが出来るのだろうか?と、講師の先生に申し訳なく思っています。「一回でも読み取れなくても、何回も繰り返し出てくる手話を組み立てて、何を言おうとしているのかを想像することも大事です」の先生の言葉を励みにしています。 先生方が、「伝えようとする気持ちが大切」とよくおっしゃいます。まだまだ手話に置き換えるのに必死で、きちんと相手の目を観たり、感情の起伏を表現出来たりとまでは行きません。 しかし、より良き手話通訳者を目指して、しっかり勉強していきたいと思っています。 |
 |
①講習会を受けて、どう思いましたか? 途中に来たので、ほとんど、柚村先生に習った事を思い出しながら、やってて、良くできたと、言われてほっとしました。楽しかった。あはは。 ②手話通訳は分かり易かったか? 5人交代だったので、それぞれ、分かりにくいとことこあった。 でも、柚村先生に習った事、同じなので、消防署の方々が、はっきり話してくれて、わかりやすいかったよ。 |
 |
西土佐手話サークル「すずらん」を、今まで色々な面で支えて下さった皆様、本当に有難うございました。 継続の気持ちは、みんなにありながら……でも、色々な事情もあり、止むを得ず『今は休もう』との答えを出しました。 今までお世話になった方々に、手話を少しでも分かって頂きたいなぁ〜と、みんなで話し合い、軍手で指文字を作っているサークルのことを知り、それなら私達にも出来るかも……と挑戦してみました。 作業中は「こうしたら?」「いや、こうしたらもっと分かり易い」「こうやったろうか?」「いや、こうやないが」などと、自分の手を使って悪戦苦闘する場面もあり、こうして完成した軍手の指文字は現在、西土佐社会福祉協議会の玄関に展示しています。 西土佐にお出での祭は、ぜひ見て下さいネ。とっても素晴らしい出来栄えです。 私たちは、手話を通して、いろいろと勉強をさせて頂きました。また、どこかで皆様に会える日を楽しみにしています。 9年間ありがとうございました!(サークル元会長) |
 |
いっぱい集まってワイワイガヤガヤして楽しかった。 肉など焼く仕事ばかりAくんと代わり代わりやった。 YくんはNくんと二つグループでやった。 夏の楽しみはバーベキュー! 久しぶりにやって楽しかった。 予想より人数が多く集まった。役員以外の参加者は協力し合ってくれた。 終わりの片付けも協力してもろうてよかった。 少し雨降ったけど気にしませんでした。交流は楽しく出来たのでよかったと思います。 |
| まずは、これまでの生活習慣を見直し、内臓脂肪を減らしましょう。 |
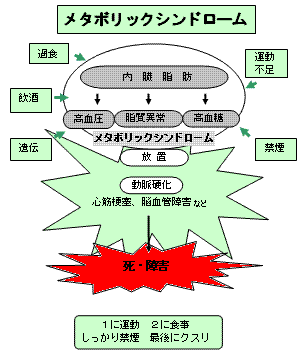
母【Nさん】通訳者養成講座修了生 わたちの名前は「佳子」と書いて「かのこ」と呼びまちゅよ。 8月9日に1ちゃいになったばかりでちゅ。 あんよはまだまだだけど、行きたい所にはハイハイスピードでどこにでもオーケーでちゅ。 わたちは、ママの顔を見つけると甘えん坊になっちゃって泣いちゃうんだ。 でも、いつもはニコニコ笑顔でちゅ。 わたちのママはちょっとボーッとしてるタイプでちゅ。 わたちはボーッとしてるママが大好きでちゅ、みなちゃんママをよろちゅくネ。 |