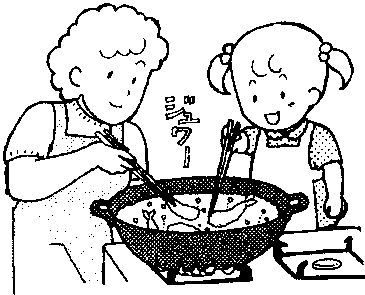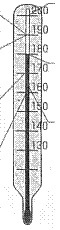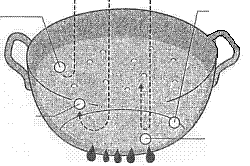デザイン賞をもらった瞬間、「まさかオレ達?」って感じでびっくりした。 苦労したことは、ペットボトルを集めて作るのに、時間も足りず、またそれぞれの都合もあり、なかなか進めずにいた。 レースの日も迫っていて、夜中まで作っていた。それほどまで熱中して取り組んだから賞を頂けたのだと思います。 仲間とのコミュニケーションには苦労をかけた。 スペシャルヒコーⅠが注目されて、僕たちは緊張したが、健聴の仲間が励ましてくれた。 次回も参加するつもりです。目標は、今回の苦労を糧に、動くようなペットボトルが作れる技術を目指したいと思っています。楽しみにしていてください。アハハ!